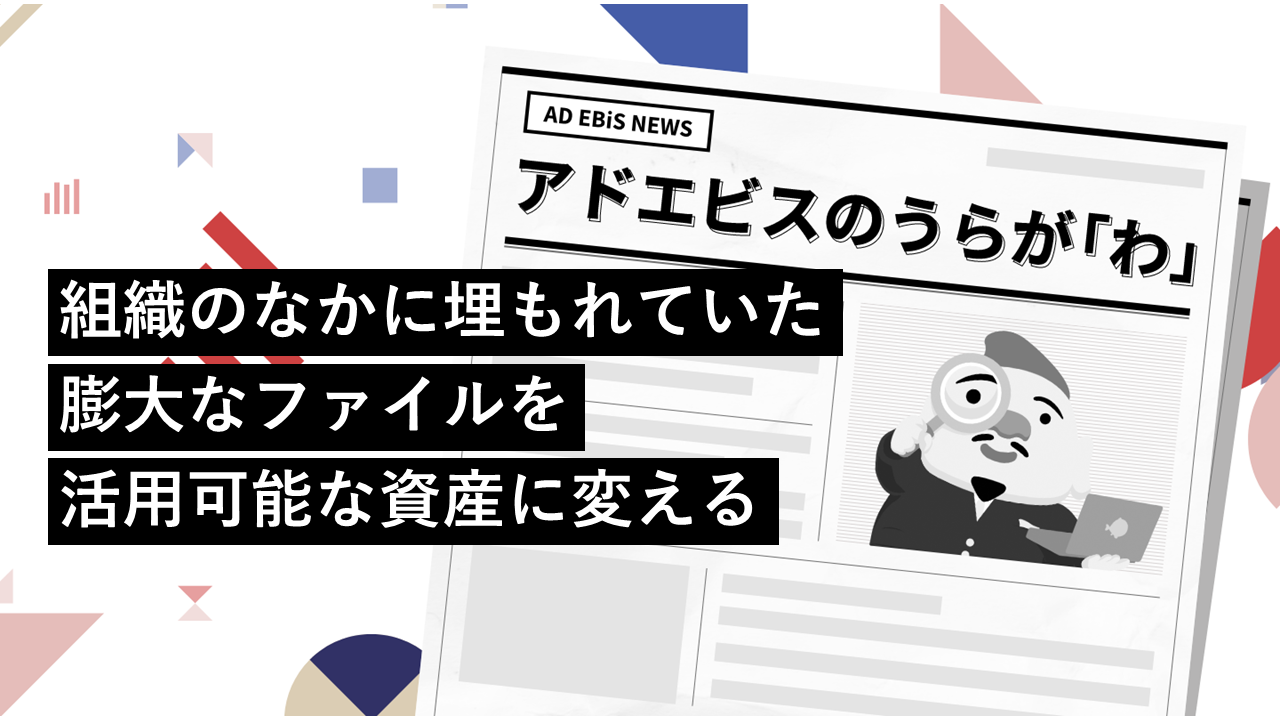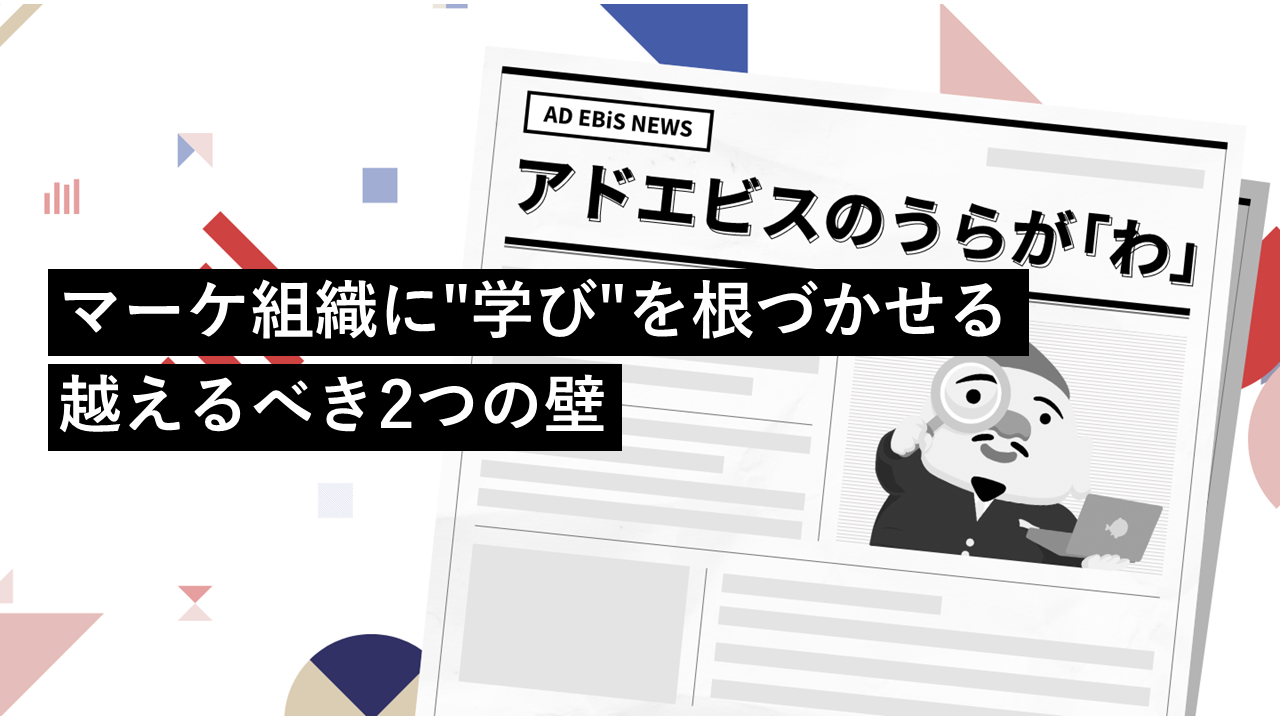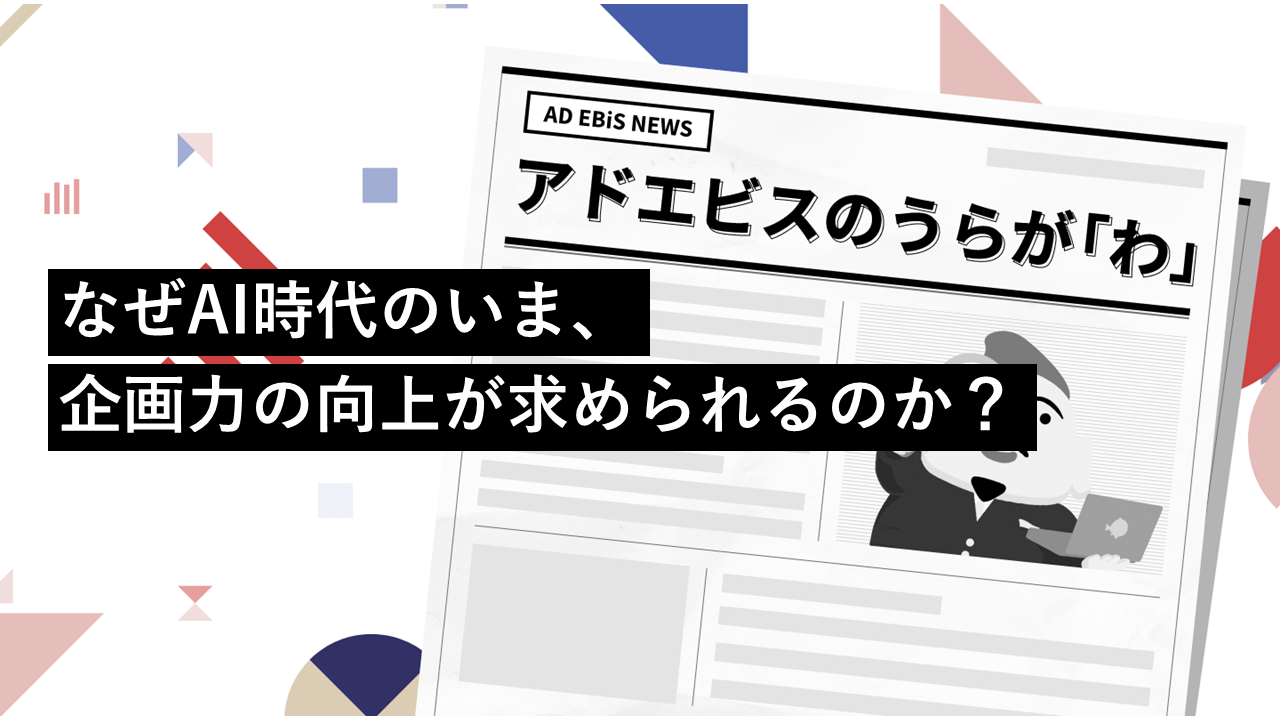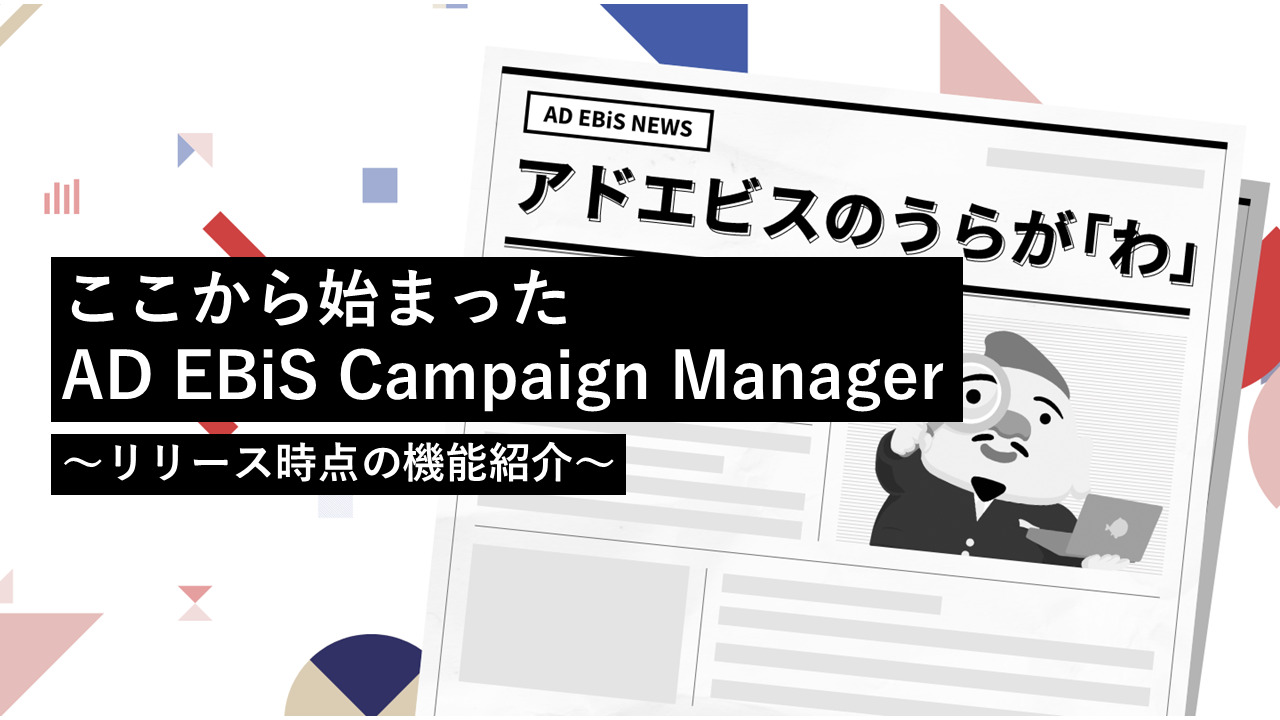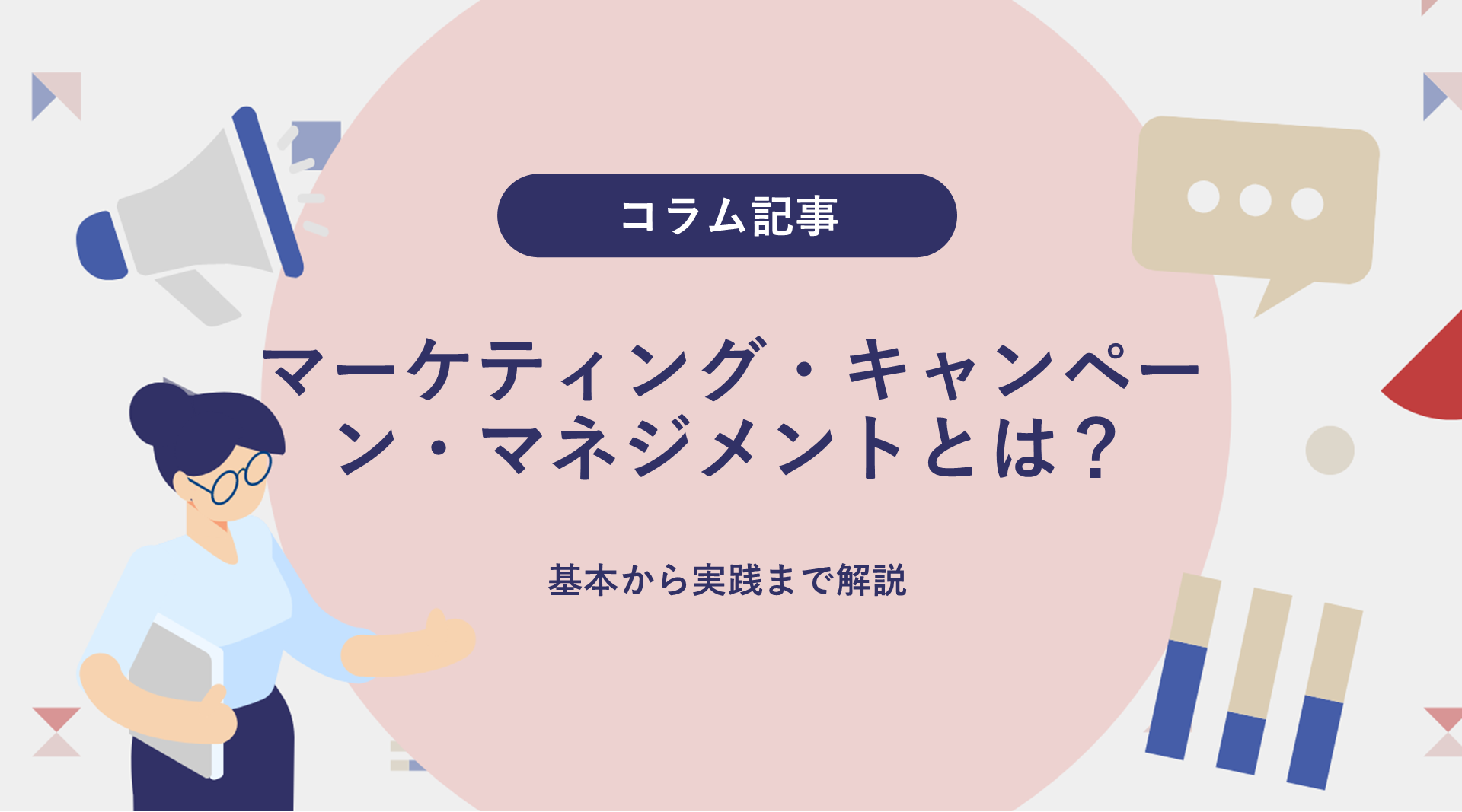【徹底解説】金融業界のマーケティング戦略・施策を解説
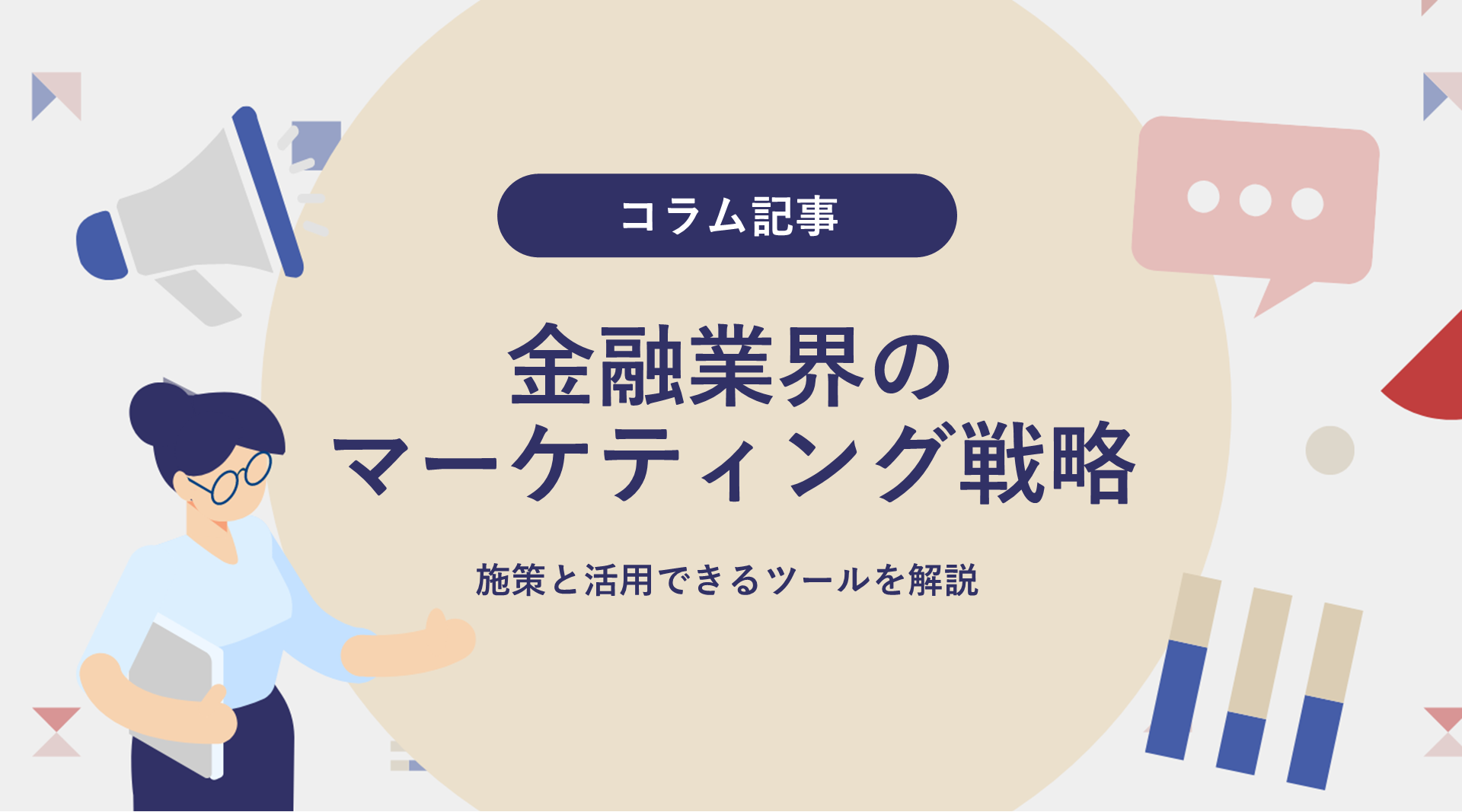
金融業界ではどのようなマーケティング戦略を行うべきか、次のような悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。
- 金融業界におけるマーケティングの必要性や取り組み方が分からない
- どのようなマーケティング戦略を行うべきか悩んでいる
本記事では、金融業界のマーケティングの必要性を解説したうえで、具体的な戦略や施策を解説します。とくにマーケティングの施策では、実際に金融業界で導入されている施策を厳選して紹介しています。金融業界でどのようにマーケティングに取り組むべきか参考にしていただければ幸いです。
1.金融業界にマーケティングが必要な理由
マーケティングとは、自社で扱う商品やサービスを顧客に購入してもらうための仕組み作りのことです。なぜ今、金融業界にマーケティングが必要なのか、3つの理由をご紹介します。
1-1.顧客の価値観が多様化している
昨今の日本は消費者のニーズが多様化しており、商品力や価格だけでは購買につなげることが難しくなってきました。そこで、マーケティングを実施して顧客の細かなニーズを捉えた戦略的な施策が求められています。
例えば、顧客のライフイベントを把握してアプローチできれば、適切なタイミングで金融商品の訴求ができます。また、顧客情報をもとに顧客をセグメントできると、多様化した価値観に寄り添う提案がしやすくなるでしょう。
このように、均一化した営業活動を脱却し多様化した価値観に対応するには、マーケティングが欠かせません。
1-2.CX(顧客体験価値)が重要視されるようになった
CX(顧客体験価値)とは、顧客が商品やサービスを選定し購入、アフターサポートを受けるまでの一連の体験のことです。商品やサービスが溢れ、価格や性能など「モノ」の価値だけでは差別化が難しくなってきた現代では、購買体験そのものが重要視されています。
金融業界でもCXを意識した「自分に寄り添ってもらえる金融サービス」や「利便性の高い金融サービス」が求められるようになりました。例えば、以前は窓口でしか処理できなかった手続きをオンライン化できると、新たな購買体験につながります。
また、顧客の要望に合わせてアプリの導入やSNSの活用など新たな顧客接点を構築できれば、顧客満足度の向上や優良顧客の獲得が見込めます。このように、CXを推進するには顧客の視点に立ち、要望や考えを汲み取るマーケティングが必要です。
1-3.テクノロジーと金融を掛け合わせたサービスが求められている
従来の金融業界は顧客と対面して直接説明や提案をすることで、購買意欲を高めてきました。しかし、消費者のデジタルシフトが進んだ現在においては、オフラインの対応だけでは差別化や購買促進が難しくなっています。
そこで、テクノロジーと金融を掛け合わせたサービスの提供が求められています。テクノロジーを活用する大きなメリットは、顧客理解を深めることができる点です。例えば、Webサイトやアプリ、SNSなどでの顧客行動データを収集できれば、顧客のニーズが見えてきます。
この分析結果を金融サービスに反映すると、より満足度の高いサービスが提供できるでしょう。金融業界にもデータの時代が到来したと言われています。オフラインで収集できるデータに限定せず、膨大なデータを有効活用しサービスをブラッシュアップしていくには、マーケティングが欠かせません。
2.金融業界のマーケティングの課題
金融業界にマーケティングは必要不可欠ですが、マーケティングに取り組むうえで2つの課題があります。どのような課題をはらんでいるのか、あらかじめ確認しておきましょう。
2-1.DX化が進みにくい
1つ目は、DX化が進みにくいことです。DX(デジタルトランスフォーメーション)とはデジタル技術を活用し、ビジネスモデルや組織、風土に変革を起こして優位性を確立することを指します。
2022年6月に金融庁が公表している「金融機関のITガバナンス等に関する調査結果レポート」を見ると、金融業界ではIT人材やノウハウの不足がDXの課題となっていることが明記されています。
また、金融業界の意識変革にも課題があり、なぜDX化やデジタル化が必要なのか理解できていない側面もあるようです。
時代に適したマーケティングを行うには、DX化がカギとなります。とくにデータを収集、分析して顧客満足度やCXを向上させるにはDXの推進が欠かせないでしょう。
※参考:金融庁「金融機関のITガバナンス等に関する調査結果レポート」
2-2.データが分断されやすく活用しづらい
2つ目は、社内でデータが分断されやすく活用しづらいところです。部署ごとで保有しているデータの共有をしていない、顧客段階ごとに管理方法が異なるなど、データの一元管理ができていない状態だと、横断的なデータ活用は難しくなります。
例えば、レガシーシステム(過去の技術や仕組みに依存しているシステムのこと)を使い続けている場合は、技術的にデータの共有や連携ができないことが多いです。
また、各部署のシステムが独立している運用方法の場合には、営業部門と事務部門、経理部門などで顧客情報の連携や共有ができないことがあります。
データが分断されていると、Web上でのマーケティング施策が最終的な成果(資料請求・申し込みなど)につながったかどうかを評価するのが難しく、誤った投資判断にもつながりかねません。施策の成果を正確に把握し効果的な施策を見極め、売上拡大につなげるためには、各フローのデータを一気通貫で把握できるデータマネジメント環境の整備が重要です。
3.金融業界のマーケティングを成功させるポイント
金融業界の課題を整理したうえで、マーケティングを成功させるために知っておきたい3つのポイントをご紹介します。
3-1.データ統合してプロセス全体を可視化する
マーケティングにおいて、施策を実施して終わりではなく効果や課題を可視化して改善を繰り返すことが重要です。定常的に効果測定を実施して改善を行うには、データの統合が欠かせません。
- 部署ごとで保有するデータが分かれている
- オフラインとオンラインでデータ管理先が分断されている
という状態ではマーケティングプロセス全体のデータを正しく把握できず、課題の解決につながるボトルネックが見えてきません。後ほど解説するツールを活用して分断されたデータを統合し、マーケティングのプロセス全体が可視化できる基盤を構築することが大切です。
3-2.明確なターゲットを定めて顧客理解を深める
顧客の価値観が多様化しているからこそニーズを正しく把握して、施策に反映させる必要があります。例えば、主婦層や富裕層、サラリーマンなど明確なターゲットを決め、ライフスタイルや課題、ニーズを分析して顧客理解を深めます。
そのうえで、顧客が必要なタイミングで必要な情報を届けることが成功につながるポイントの1つです。顧客理解を深めるときには1つ目のポイントで触れたデータを活用し、ユーザーの行動や属性などを分析するとスムーズに進められます。
3-3.顧客との接点を複数用意する
顧客のデジタルシフトにより、SNSやWebサイト、アプリなど新たな接点が構築しやすくなりました。接点によりターゲットや目的が異なるため、1つの施策にとどまらず複数の接点を用意することが大切です。
例えば、投資信託の情報を動画で配信していたとしましょう。この場合、投資信託に興味があり、かつ普段から該当の動画プラットフォームを利用している見込み顧客としか接点を持つことができません。このケースでは、他のプラットフォームも開拓して接点を増やす必要があるでしょう。できるだけ顧客一人一人に合わせた接点が構築できるよう検討し、顧客体験価値を向上させることが大切です。
4.金融業界のマーケティングで活用できる戦略一覧
実際に、マーケティングに取り組むときには下記のようなマーケティング戦略を活用できます。戦略に応じて向いているフレームワークが異なるため、概要を把握して使い分けてみましょう。
4-1.STP戦略
セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニングの頭文字を取った基本的なフレームワークです。
- セグメンテーション:顧客ニーズを細分化する
- ターゲティング:セグメンテーションで可視化したニーズからターゲットを決める
- ポジショニング:ターゲットに対する自社商品の優位性を設定する
活用できるシーン
- マーケティング戦略を明確化したいとき
- 自社商品の優位性を明確化したいとき
4-2.3C分析
Customer(顧客)・Company(自社)・Competitor(競合)の頭文字を取ったフレームワークです。立場の異なる3つの視点から分析することで、成功要因を導き出します。
- Customer:市場や顧客のニーズを分析する
- Company:自社の強みや優位性を分析する
- Competitor:競合他社の強みや優位性を分析する
活用できるシーン
- マーケティング戦略の方針を決めるとき
- 競合他社と明確に差別化したいとき
4-3.ファイブフォース分析
競争要因を5つに分類し分析することで、自社の優位性を明確にするフレームワークです。
- 業界内での競争:業界規模や成長率、業界内での競合他社を分析する
- 新規参入者:新たに市場に参入する可能性がある企業や業界を分析する
- 代替品の存在:自社の商品やサービスの代替品を分析する
- 売り手の交渉力:売り手との関係性やコストを分析する
- 買い手の交渉力:顧客と自社との関係性や販売コストを分析する
活用できるシーン
- 市場での自社の優位性を明確化したいとき
- 現状を整理しマーケティングにおける課題を明確化したいとき
4-4.SWOT分析
Strengths(強み)・Weaknesses(弱み)・Opportunities(機会)・Threats(脅威)の頭文字を取ったフレームワークです。自社の現状を内部環境と外部環境に分けて整理できます。
- Strengths:自社の強みや特徴を分析する
- Weaknesses:自社の弱みや競合他社より劣っている点を分析する
- Opportunities:自社の商品やサービスに好影響を与える外部環境を分析する
- Threats:自社の商品やサービスに悪影響を与える外部環境を分析する
活用できるシーン
- 現状を把握したうえで適切なマーケティング施策を考えたいとき
4-5.PEST分析
Politics(政治)・Economy(経済)・Society(社会)・Technology(技術)の頭文字を取ったフレームワークです。自社を取り巻く外部環境がどのような影響を与えるのか分析できます。
- Politics:自社に影響を与える法律の変化や政策などを分析する
- Economy:自社に影響を与える景気の変化や株価などを分析する
- Society:トレンドやライフスタイルの変化などを分析する
- Technology:自社に関連する技術やテクノロジーの進化を分析する
活用できるシーン
- 今後の市場変化を踏まえたうえでマーケティング施策を決めたいとき
- 外部環境の変化や脅威を把握したうえでマーケティング施策を立てたいとき
4-6.バリューチェーン分析
自社の事業を機能別に分類し、どの工程でどの程度の付加価値が生じているのか分析するフレームワークです。バリューチェーンを可視化し、工程別にコストや強み、弱みを分析します。
活用できるシーン
- 自社の強みを理解しマーケティング施策を立てたいとき
- 利益の拡大や他社との差別化を意識したマーケティング施策を立てたいとき
4-7.4P分析
Product(商品)・Price(価格)・Place(流通)・Promotion(販売促進)の頭文字を取ったフレームワークです。
- Product:自社の商品やサービスの強みを分析する
- Price:商品やサービスの価格の妥当性や利益率を分析する
- Place:自社の商品やサービスに合う販売方法を分析する
- Promotion:現在実施しているプロモーションの手法や効果を分析する
活用できるシーン
- マーケティングにおいて販売方針を明確化したいとき
- 自社の強みを理解しマーケティング施策を立てたいとき
5.金融業界で導入したいマーケティング施策
マーケティング戦略に活用できるフレームワークが理解できたところで、実際に金融業界で導入されている具体的なマーケティング施策をご紹介します。
| 金融業界で導入したいマーケティング施策 | |
|---|---|
| オウンドメディア | Webサイトやブログなどのメディアを運用する |
| リスティング広告 | 検索エンジンの検索結果に連動して広告を表示する |
| メールマガジン | メールを利用して定期的に情報発信をする |
| SNS | X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSを運用する、もしくはターゲット分析に活用する |
| 動画コンテンツ | YouTubeやライブ配信などの動画コンテンツを運用する |
| セミナー | 特定のテーマを設けて興味がある人をオンライン・オフラインで集客し開催する |
| 自社アプリ | 銀行口座と紐づけしたアプリなど自社独自のアプリを開発する |
自社の課題や目的に応じて、どのような施策を導入するべきか検討してみてください。
5-1.オウンドメディア
オウンドメディアとは、Webサイトやブログなど自社で保有するメディアのことです。金融業界とオウンドメディアは相性がよく、銀行や証券会社、ローン会社などで導入されています。
金融業界がオウンドメディアを活用する大きなメリットは、2つあります。
1つ目は、顧客との接点の構築です。オウンドメディアで情報を発信すると、今まで店舗に足を運んだことのない潜在顧客にもアプローチできるようになります。
例えば、女性をターゲットとしたお金に関するメディアを運用すれば、家計のやり繰りや貯金などに興味を持つ女性との接点が生まれます。すぐには金融商品を購入する予定はなくても、将来的に検討してもらえる可能性があります。
2つ目は、信頼性の獲得です。金融業界で扱う商品は、理解が難しいものや仕組みが複雑なものが含まれています。オウンドメディアで専門性の高い情報や商品を丁寧に説明する情報などを発信することで、顧客の不安や悩みを払拭できます。
オウンドメディアが向いているケース
- 顧客との新たな接点を構築したい
- 自社や商品、サービスの信頼性やブランド力を高めたい
5-2.リスティング広告
リスティング広告とは、検索エンジンの検索結果に連動して広告が表示できるWebマーケティング手法です。GoogleやYahoo!などの検索エンジンで特定のキーワードを検索したときに、キーワードに応じて検索ページの上部や下部に表示されます。
リスティング広告は、オウンドメディアやLP(ランディングページ)などへの流入数を増やせるところが大きな魅力です。オウンドメディアやLPを作成してもアクセス数がなければ、思ったようなマーケティング効果を得られません。とくに運用開始時はリスティング広告を組み合わせることで、マーケティング効果を高められます。
また、リスティング広告はオウンドメディアやLPと関連性の高いキーワードで検索をしている顕在顧客に対してアプローチができるところもメリットです。自社の商品やサービスに興味を持ってくれそうな顧客に対して、積極的にアピールできます。
リスティング広告が向いているケース
- オウンドメディアやLP(ランディングページ)などへの流入数を増やしたい
5-3.メールマガジン(メルマガ)
メールマガジンは、メールを利用して定期的に情報発信をするマーケティング施策です。金融業界はメールマガジンの開封率が高いため、他の業界よりも効果が見込めます。選定したターゲットの悩みや要望に合う情報を発信することで、購買促進や信頼性の向上につながります。
また、メールマガジンはターゲットに応じて配信内容を変更することがポイントです。マーケティング活動の自動化・効率化ができる「MA(マーケティング・オートメーション)ツール」を活用すれば、リード(見込み顧客)の検討レベルに合わせて自動配信することができます。例えば、投資に興味がある顧客には投資に関する情報を、積立預金をしている顧客には資産運用の情報を配信するなど、セグメントしやすいところが特徴です。顧客の行動データや顧客情報をもとにセグメントができれば、より精度の高いマーケティングが実現できます。
メールマガジンが向いているケース
- ターゲットに応じた情報発信を行いたい
5-4.SNS
SNSとは、X(旧Twitter)やInstagramなどインターネット経由でコミュニケーションが取れるサービスのことです。インターネットやモバイル通信が普及したことで、SNSを活用したマーケティングも活発化しています。総務省が公表している「令和3年通信利用動向調査」によると20代~40代の85%以上がSNSを利用しています。
実際にメガバンクではX(旧Twitter)やInstagram、FacebookなどのSNS運用を実施しており、キャンペーン情報やノウハウ、自社のニュースなどを発信しています。SNSはリアルタイムで情報を共有できるため、キャンペーンやイベントの告知などに活用できるところが特徴です。
また、SNSでの口コミや投稿への反応を分析して、マーケティングに生かすことも可能です。例えば、セミナーごとの反応を比較し、どのようなセミナーが興味を集めているのか分析ができます。
SNSが向いているケース
- リアルタイムで情報を発信したい
- より多くのターゲットにアプローチしたい
- 自社の商品やサービスに対する風潮や口コミを分析したい
5-5.動画コンテンツ
YouTubeやライブ配信などの動画コンテンツも、金融業界と相性がいいと言われています。商品やサービスによっては理解が難しく、テキストだけでは伝わりにくいケースがあります。
動画にすることで複雑な仕組みを分かりやすく解説できるのはもちろんのこと、親しみやすさや楽しさをプラスできるところが特徴です。また、動画では下記のように自社のブランド力や信頼性を高める情報を分かりやすく伝えられます。
- 専門家による解説やQ&A
- 自社の商品やサービスの強みや活用事例
- 金融業界に関連するトレンド情報
動画コンテンツが向いているケース
- ブランド力や信頼性の向上を目指したい
- 他社との差別化を図りたい
5-6.セミナー
セミナーとは、特定のテーマを設けて興味がある人を集客し開催するマーケティング施策です。オフラインとオンラインの双方で開催できます。
セミナーを定期的に実施しているメガバンクは一定数あり、資産運用や投資信託など商品やサービスに興味を持ってもらえるテーマを扱っています。セミナーの参加者はテーマに興味や関心があることが前提なので、検討度の高い顧客にアプローチできるところが特徴です。
また、セミナーは多くの参加者を相手に開催できるため、営業効率が向上します。例えば、一度のセミナーから5人の見込み顧客を獲得できれば、定期的にセミナーを開催するだけで安定して見込み顧客を創出できます。
セミナーが向いているケース
- 検討度や関心度の高い顧客を対象としたマーケティング施策を実施したい
- 見込み顧客獲得にかかる手間やコストを削減したい
5-7.自社アプリ
金融業界では自社で独自のアプリを作成し、マーケティングに活用しているケースが目立ちます。アプリの種類の一例としては、下記のようなものが挙げられます。
- 銀行口座の残高確認や振込、入出金明細照会ができる管理アプリ
- 口座の申し込みができるアプリ
- 収支管理ができるアプリ
アプリ経由での銀行口座の情報確認や振込などに加え、自社の情報発信やお知らせ通知を兼ね備えているアプリもあります。アプリを導入することで顧客と新たな接点が生まれ、アフターサポートや新商品の販売促進などに活用できます。
導入に手間やコストがかかる施策ではありますが、一度アプリをダウンロードすると長い間接点を持ち続けられるところがメリットです。
自社アプリが向いているケース
- 顧客との新たな接点を構築したい
- 顧客体験価値や顧客満足度の向上につながる施策を検討したい
6.おわりに
本記事では、金融業界にマーケティングが必要な理由や具体的な戦略、そして導入すべき施策をまとめて解説しました。
データの分断やなかなか進まないDXが課題となっている金融業界では、データを一元管理して分析や効果測定ができる環境を整えることがマーケティングの成功へとつながります。
アドエビスであれば
- ユーザーがコンバージョンに至るまでの経路を一画面で可視化
- Salesforceなどの外部ツールと柔軟に連携し、オンライン・オフラインのデータ統合が可能
- 流入施策の効果測定データと最終的な売上データを連携し、LTVやROIといった広告から得られた収益データを算出可能
といった強みがあり、金融業界のマーケティングを手厚くサポートします。
実現方法などの詳細は、下記事例をご確認ください。
▶売上3倍に貢献!コンバージョンフローを活用した分析方法とは?
▶【理想のレポート別】アドエビスとGA4の違い
▶CV数が1.3倍に!GA4ではできなかったWeb × オフライン統合評価をアドエビスで実現
アドエビスの機能やレポート方法についてはアドエビスカスタマーサクセスチーム(adebis_success@ebis.ne.jp)にぜひご相談ください!